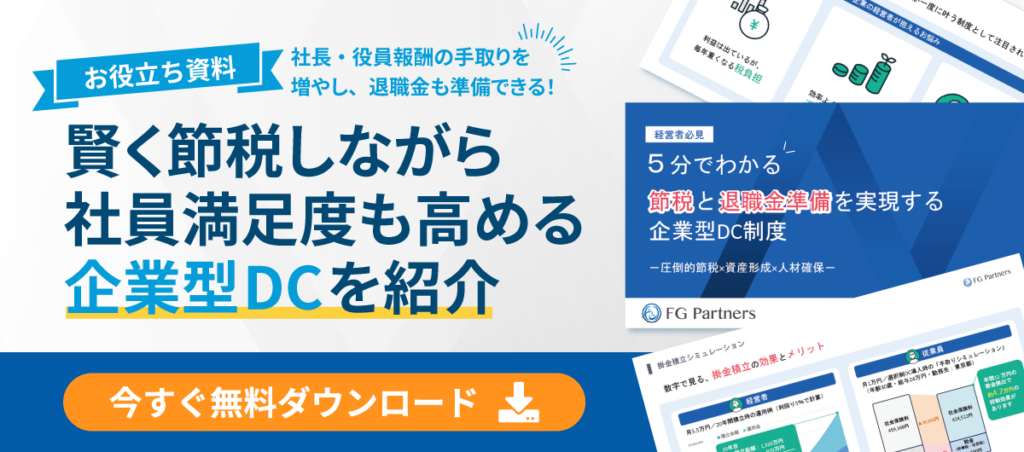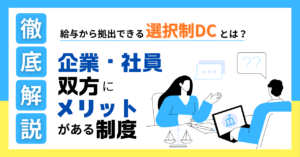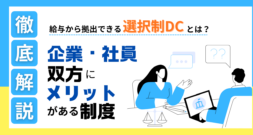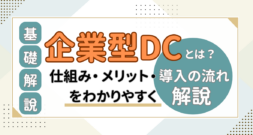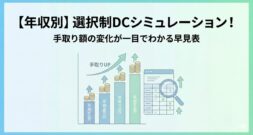いま注目の「企業型DC(企業型確定拠出年金)」とは?中小企業の退職金制度が変わる理由
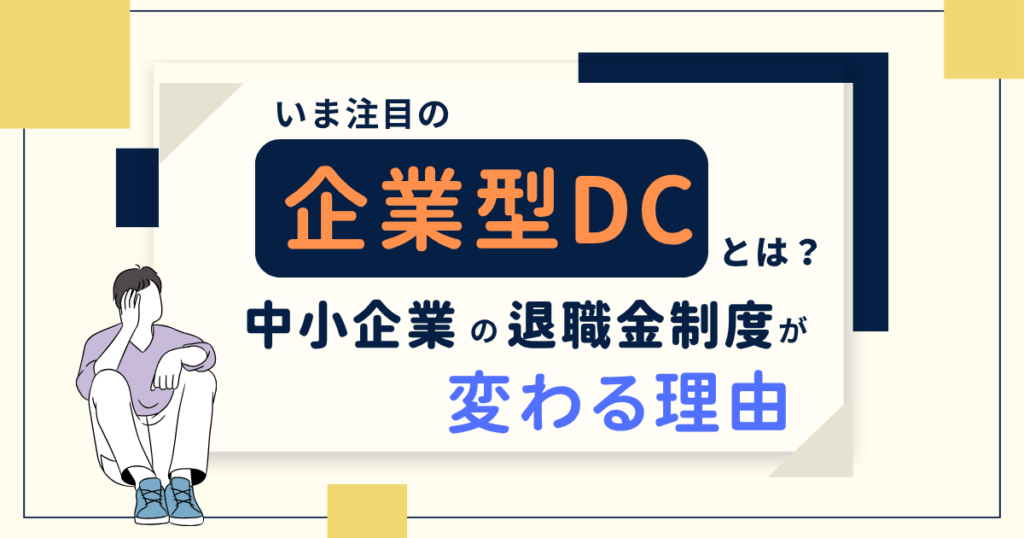
目次
はじめに
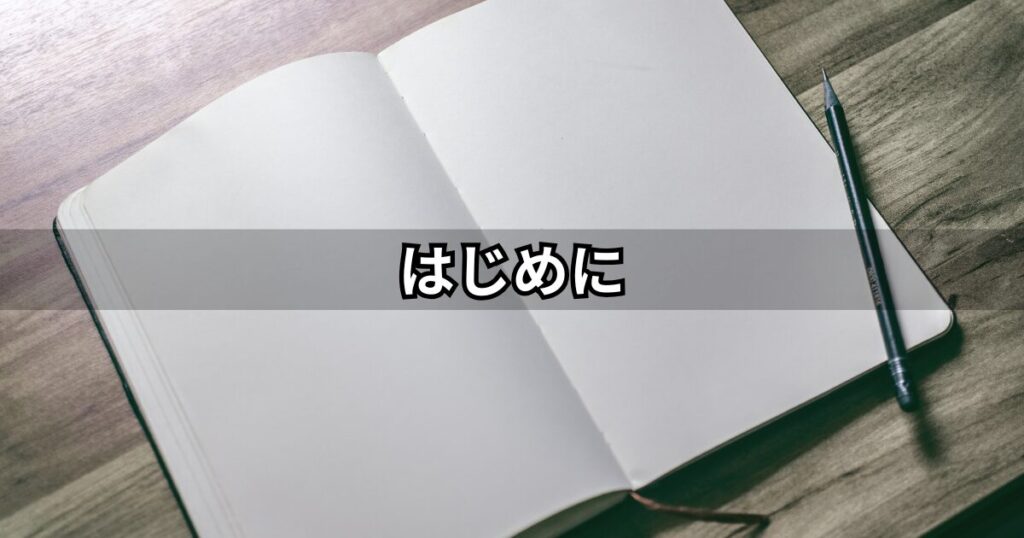
人生100年時代と言われる現代、老後の資産形成への関心はますます高まっています。
そんな中、特に中小企業の間で、新たな退職金制度として注目を集めているのが「企業型DC(企業型確定拠出年金)」です。
「聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。
企業型DCは、これまでの退職金制度とは大きく異なり、企業と従業員の双方にメリットをもたらす可能性を秘めた制度です。
本記事では、企業型DCとは何か、なぜ今注目されているのか、そして、それが中小企業の退職金制度をどう変えていくのかを分かりやすく解説します。
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは?
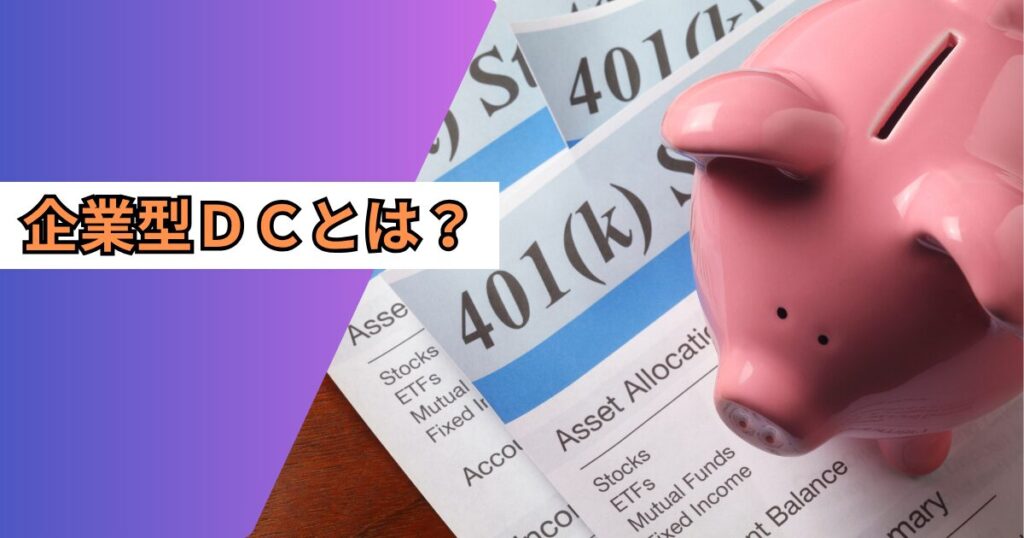
企業型DCとは、企業が掛金を拠出し、従業員(加入者)自身がその資金を運用して、将来の退職給付額を決める制度です。
従来の多くの退職金制度(確定給付年金など)は、将来受け取れる給付額が約束されている代わりに、企業が運用責任を負っていました。
一方、企業型DCは「確定拠出」という名前の通り、企業が拠出する掛金額は確定していますが、将来受け取る額は従業員自身の運用成果によって変動するのが最大の特徴です。
従業員は、企業が用意した複数の金融商品(投資信託、保険商品、定期預金など)の中から、自身の判断で投資先を選び、資産を育てていきます。
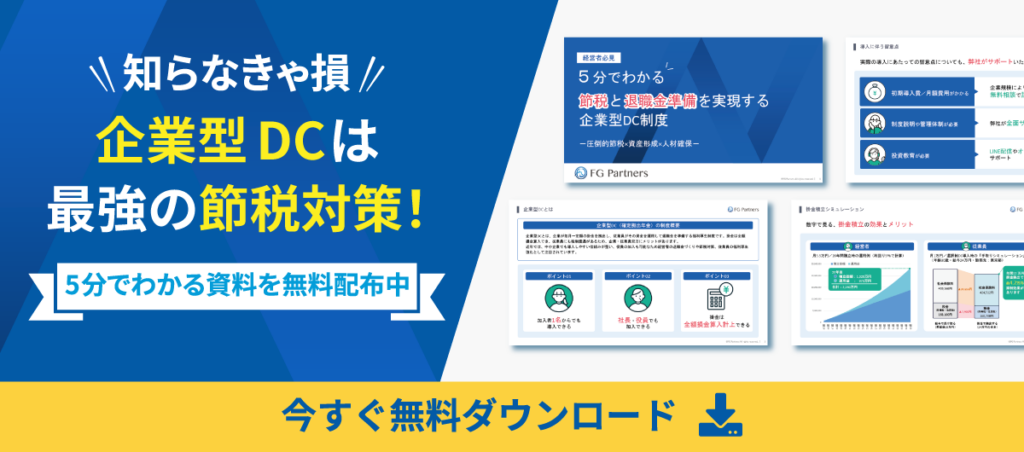
中小企業の退職金制度、主な選択肢は?

企業型DCに注目が集まる中、そもそも中小企業にはどのような退職金制度の選択肢があるのでしょうか。
代表的な制度を簡単に見てみましょう。
- 中小企業退職金共済(中退共)
国が運営する中小企業向けの退職金制度です。企業は掛金を納付するだけでよく、管理が簡単なのが特徴です。
多くの企業で採用されていますが、運用は国に任せる形となります。 - 確定給付企業年金(DB)
将来の給付額を企業が約束する制度です。
従業員にとっては安心感がありますが、企業側は運用責任を負い、市況によっては将来的な追加負担のリスクがあります。 - 特定退職金共済(特退共)
商工会議所などが運営する制度で、仕組みは中退共に似ています。地域や業種に根差した運営が特徴です。 - 社内での準備(退職一時金)
企業が自社内で資金を積み立て、退職時に一時金として支払う方法です。
制度設計の自由度は高いですが、計画的な資金準備が不可欠であり、企業の経営状況に左右されるリスクがあります。
これらの選択肢と比較することで、次に解説する企業型DCの特徴がより明確になります。
なぜ今、中小企業で「企業型DC」が注目されるのか?

これまで大企業が中心だった企業型DCが、なぜ今、中小企業の間で導入が広がっているのでしょうか。
その背景には、いくつかの重要な理由があります。
企業側の負担が明確で、将来のリスクを軽減できる
従来の退職金制度では、将来の給付額を約束するために、企業は運用環境の悪化(低金利など)によって追加の資金負担(積立不足)が発生するリスクを抱えていました。
企業型DCでは、企業は毎月決められた掛金を拠出するだけで責任を果たせます。
将来の追加負担リスクがないため、コストが明確になり、中小企業でも計画的に制度を運営できます。
中小企業でも導入しやすくなった
かつては、企業型DCの導入は手続きが複雑でコストも高く、大企業が中心でした。
しかし近年、金融機関などが中小企業向けに特化した、シンプルで低コストな導入プランを提供するようになりました。
これにより制度導入のハードルが大きく下がり、従業員数が少ない企業でも導入しやすくなっています。
「選択制」で、より柔軟な制度設計が可能に
給与の一部と企業型DCの掛金、どちらで受け取るかを従業員自身が選べる「選択制DC」という仕組みも普及しています。
これにより、企業は人件費を増やすことなく制度を導入でき、従業員はライフプランに合わせて資産形成を始めるかを選択できるため、双方にとって導入のハードルがさらに下がります。
※選択制DCについての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
(給与から拠出できる選択制DCとは?企業・社員双方にメリットがある制度を徹底解説)
人材の確保・定着につながる福利厚生
少子高齢化が進み、人材獲得競争が激化する中で、魅力的な福利厚生は企業の大きな武器となります。
充実した退職金制度である企業型DCを導入することは、「従業員の将来を大切にする企業」というメッセージとなり、優秀な人材の採用や離職率の低下に繋がります。
税制上の大きなメリット
企業型DCには、企業と従業員の双方にとって大きな税制優遇措置があります。
【企業のメリット】
- 拠出した掛金は、全額損金として計上可能です。
【従業員のメリット】
- 掛金が非課税:企業が拠出した掛金は、従業員の給与所得とは見なされず、所得税・住民税がかかりません。
- 運用益が非課税:通常、金融商品の運用で得た利益には約20%の税金がかかりますが、企業型DCの口座内での運用益は非課税です。
- 受け取り時にも控除:将来、年金や一時金として受け取る際にも、「公的年金等控除」や「退職所得控除」といった大きな控除が適用されます。
制度の柔軟性とポータビリティ
従業員は転職や独立の際に、それまで積み立てた資産を持ち運ぶ(移換する)ことができます。
新しい勤務先が企業型DCを導入していればそちらに移せますし、個人型のiDeCo(イデコ)に移換することも可能です。
これにより、キャリアプランが多様化する現代の働き方に柔軟に対応できます。
従業員にとっての注意点

多くのメリットがある一方で、従業員側には注意すべき点もあります。
- 運用は自己責任:運用成果によっては、元本割れするリスクもあります。制度を導入する企業側は、従業員が適切な判断を下せるよう、継続的な投資教育を行うことが求められます。
- 原則60歳まで引き出せない:老後の資産形成を目的とした制度であるため、原則として60歳になるまで資産を引き出すことはできません。
まとめ
企業型DCは、将来の負担リスクを軽減したい企業と、税制優遇を受けながら主体的に資産形成を行いたい従業員の双方のニーズに応える、まさに「一石二鳥」の制度です。
特に、経営基盤を安定させつつ、人材という最も重要な資産を確保したい中小企業にとって、企業型DCは退職金制度の新たなスタンダードとなり得る強力な選択肢と言えるでしょう。
自社の福利厚生や退職金制度を見直す際には、ぜひ企業型DCの導入を検討してみてはいかがでしょうか。